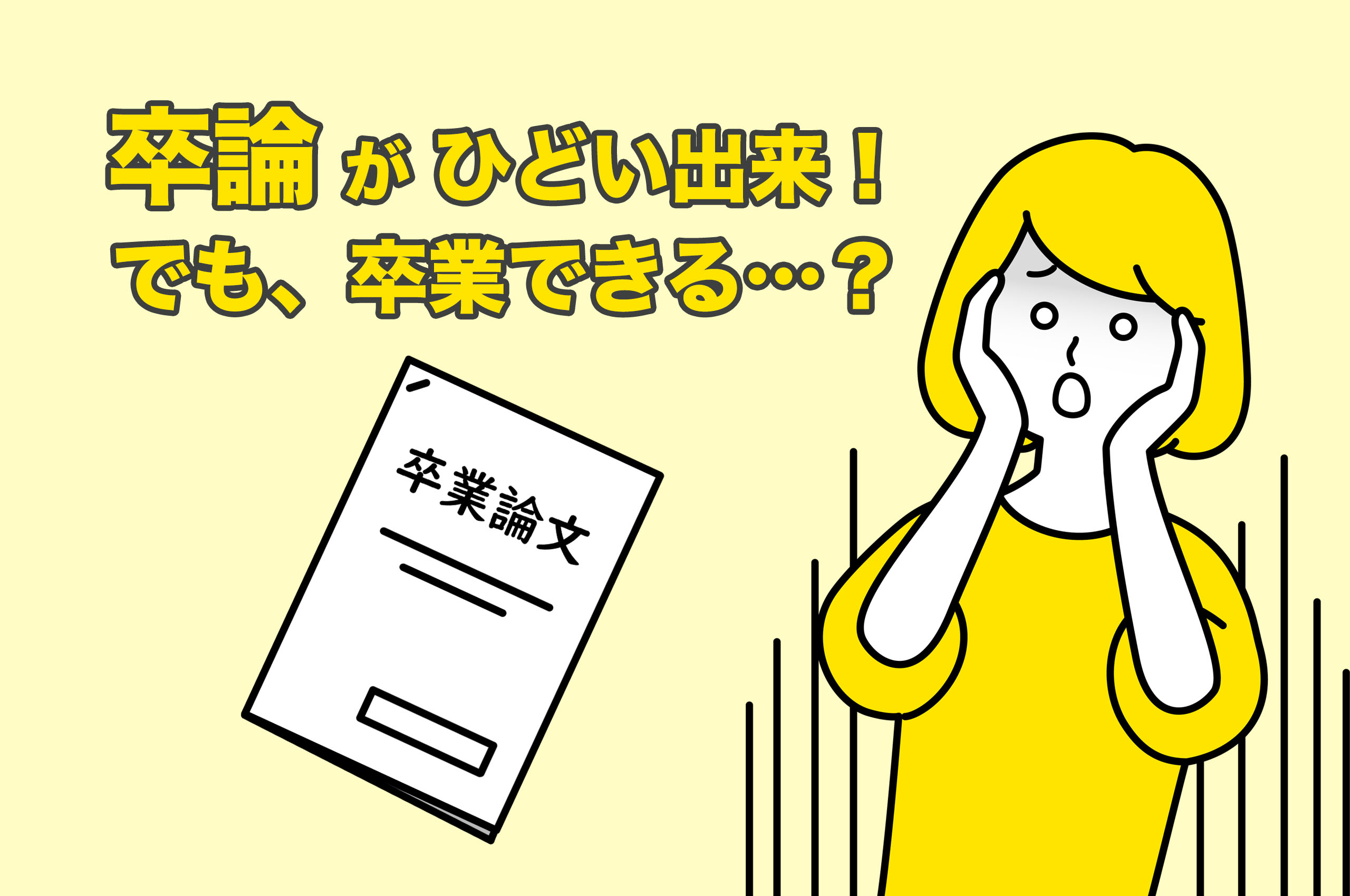「データが足りなくて卒論書けるかわからない…」
「周りと比べて出来がひどい気がする…」
このような不安を感じている方も、きっと多いのではないでしょうか。
私も書く前は不安でした。
しかし、いざ書き終わって周りの人と比べてみると、「あっ意外とこれで大丈夫なんだ」とクオリティは関係ないことに気づきました。
本記事では、卒論に不安を抱えている方へ向けて、卒論を終えたばかりの私の経験をお話ししたいと思います。
理系の卒論の出来がひどくても大丈夫?
結論から先に申し上げますと、よほどひどい出来でない限り落とされることはありません。
なぜかと言いますと、理由は大きく分けて2つあります。
- 研究成果はそこまで重要視されていない
- 留年させても、研究室にとってあまりメリットがない
研究成果はそこまで重要視されていない
学部生には研究成果はそこまで重要視されていないので、ひどくても問題ないです。
そもそも卒業研究は、1年にも満たない期間で仕上げなければなりません。
多くの方は1~3月に研究室配属が決まり、研究テーマを決め、装置の使い方やその分野について勉強し、研究室内のルールや雰囲気などに順応し、ようやく実験を始めることができます。
研究室によっても違いはありますが、7月頃から本格的に実験に取り掛かる人もいました。
僕の場合は、研究テーマは引継ぎだったため、比較的早く実験に取り掛かれましたが、それでも初めの方は、効率よく実験を進められませんでした。
使用する試料や装置に対する知識も無かったため、計画を立てたとしても上手くいくことの方が少なかったです。
また院進する人は、夏ごろに大学院入試があり、少なからず時間を割く必要があります。
僕は外部院進だったので、試験勉強と研究の両立は結構大変でした。
あわせて読みたい
一方で就職する人は、就活をしなければならないため、人によっては院試の勉強よりも多くの時間や体力、気力が必要になるでしょう。
このように、1年間まるまる研究に時間を割くことは難しく、実験系の研究をする方は特に、最初は上手くいかないことばかりです。
そんな状態ですごい研究成果を挙げられる人はごく稀です。
よほど教員の指導が優れているか、本人が並外れて優秀であるかのどちらか、あるいは両方でないと難しいように思います。
そのため、卒業研究の成果を重要視している教員はほとんどいません。
こういった事情を理解したうえで、あなたの発表を聞いています。
僕の指導教員もそのような発言をしていました。(笑)
どちらかというと、結果よりも
- なぜその手順を踏んだのか
- なぜそのような考察になるのか
- 目的と結論の整合性
などの論理展開を見ています。
大学や学部によっても異なるとは思いますが、僕の所属していたところでは、評価基準にもそのような記述がありました。
まずは結果に関してはあまり気負わずに、卒論に取り組めばいいと思います!
留年させても、研究室としてあまりメリットがない
4年生は研究室というコミュニティに配属され、基本的にはそこで実験を進めます。
教授としては、4年生の卒論が終わり次第、修士に向けて研究をなるべく早く始めて欲しいものです。
また卒業する予定の人に関しては、卒業させずにもう1年あるいは半年ほど残ってもらってもあまりメリットがありません。
言い方は少し良くないですが、就活をして卒業する気満々の4年生に研究室に残ってもらっても、教授自身にとって良いことはほとんどないのです。
雑用をやらされる研究室もあるみたいですが、それが理由で卒業させずに残されることはないです。
以上より、内容がひどくても大丈夫?対する結論としては、よほどひどくなければ大丈夫でしょう。
では、あまりにも無茶苦茶な場合はどうなるのでしょうか。
どうなったら留年してしまう?ひどすぎた場合は?
僕が卒業研究発表会に参加したときに、「中々これはどうなの?」というような研究成果で発表をしている方々が何名かいました。(笑)
ですがその方々も、普通に卒業資格を得たようです。
何度も述べていますが、研究成果がダメダメでも、話にある程度筋が通っていれば卒業できます。
そんな中でも、卒業資格を得られなかった方が、1人いました。
その方は1年間全くと言っていいほど学校に来ず、研究活動を一切行っていなかったそうです(その研究室の友人に聞いた話ですが)。
留年してしまうような方は、その大半が学校に行かず、研究活動をしていなかった場合の方のみだと思います。
普通に研究室に行って研究していれば大丈夫なので、ご安心ください。
卒論を書く時のポイント
卒論を書き終えたばかりの学生がアドバイスするのもおこがましいですが、周りの友人などの卒論を読んで、わかりやすかった卒論の特徴などをまとめてみます。
- ストーリーができており、話が通っている
- 一目でわかりやすいイラストが添付してある
- Why?に対して、きちんと説明がある
以上の3つが、僕が感じたわかりやすい卒論の特徴です。
ストーリーができており、話が通っている
ストーリーというのは、
分野の概要・背景 → 目的 → 研究手段 → 結果・考察 → 結言
という論理展開があり、話が繋がっていることです。
現時点では解決されていない問題を研究をするわけですから、その背景をもとに目的を立て、その目的をどうしたら解決できるのかを明確に記す必要があります。
ストーリーを作るには、その分野に対する理解と、筋の通った解釈が必要になります。
ある程度真面目に研究に取り組んでいれば、卒論を書く時期にはそこまで悩むことは無いと思います。
異なる分野の人たちにも分かりやすく伝えるためには、ストーリーが非常に重要であると感じました。
例えば、
人口増加 → エネルギー問題 → 再生可能エネルギー → 太陽電池 → 色素増感太陽電池 → 低コスト高変換効率が期待 → 電子移動機構が解明されていない → ○○という方法が××という理由で有効であるため、実験を行った
といったように、誰でも理解できる論理を立てることが理想です。
何度も言いますが、成果はそこまで問われません!
予想と違った結果が出ても、きちんとそこの説明を補えば問題なしです。
一目でわかりやすいイラストが添付してある
なるべく分かりやすいイラストを文章の間にちりばめておくことがおすすめです。
どのような機構で反応が進むのか、どのような測定のメカニズムなのかなど、初めて見た方にも理解しやすいイラストを示して説明すると丁寧でいいと思います。
Why?に対して、きちんと説明がある
なぜこの目的を立てたか?なぜその方法で取り組んだか?なぜそのような結果がでたのか?
のように、なぜ?と感じる疑問点についてきちんと答えを用意することが大事です。
ずっと同じ内容のことに取り組んでいると、「この部分は当たり前すぎて説明もいらないだろう」と感じて説明が不足する部分が生まれがちです。
初めてその内容を知る人からすると、なぜそういう流れになったのか理解できないことがあります。
僕も発表練習の時に、そういった質問もされましたし、逆に他の方の発表で理解できないこともありました。
卒論作成に取り掛かる時は、丁寧すぎるくらいでいいと思います。
後に教授から修正があれば削ればいいだけの話です。
ひどい出来でも留年はないし、話の筋が通っていればOK
卒論についてまとめると、
- ある程度研究室に行って、データもがあれば留年することはない!
- 卒論の内容で大切なのは話の筋が通っているかどうかで、成果はあまり気にしない!
以上になります。
発表の時は、短い時間で分かりやすく簡潔に伝える必要があるため、そこでもやはり大事なのは話の筋が通っているかだと思います。
卒論に不安を抱えている方の参考になれば嬉しいです。
卒論作成頑張ってください!
あわせて読みたい