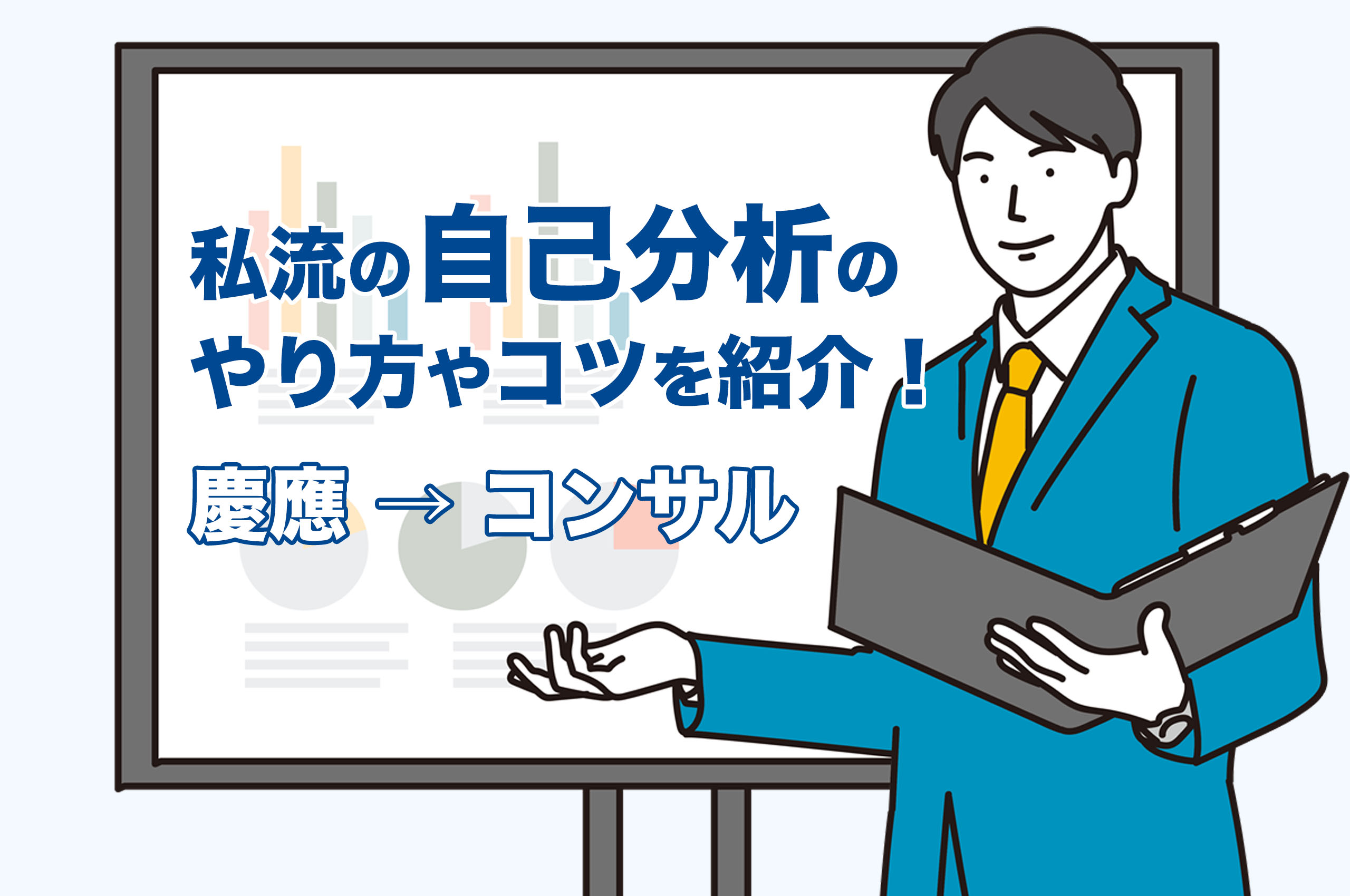これまで様々な自己分析に取り組んできたものの、本当に効果が出ているのか分からない方は多いのではないでしょうか?
私は3年生の4月から就活に本気で取り組み始め、4年生の4月には複数の企業から内定をいただきました。
1年就活を経験したことで自己分析の方法も確立できてきたので、今回は、これから就職活動を進めていく方々に向けて、
私が実践した「後悔しない自己分析」のやり方とポイントを徹底解説していきます!
就活の自己分析について
自己分析は自分を言語化する作業
自己分析の進め方について考える前に、まずは「自己分析とは何か?」について整理していきましょう。
就活における自己分析とは、「自分が本当にやりたいこと(=やりたい仕事)」を見つけるために自身を言語化する作業だと考えています。
就職活動では、日本国内だけでも350万社以上の企業から入社する1社を選択することになります。
これまでの高校、大学受験とは選択肢の数が大きく異なるのです。
そのような条件の下で自分自身にあった業界・企業を見出すためには、「社会人になりどんなことがやりたいのか?」という「自身の未来」をより深く考えなければなりません。
そのための手段として自己分析があります。
自己分析は自分の「行動」がどんな「感情」に由来するのかを理解する作業
「真にやりたいこと」を見出すためには、これまでの自身の「行動」はどのような「感情」に由来するのかを理解することが必要です。
私のおすすめは、次の方法です。
- 「経験」を洗い出し
- それぞれの経験の「感情の動き」を分析
「経験」を洗い出す
まずは、これまでの人生で自分が経験してきたことを洗い出しましょう。
洗い出す段階で、人生の大きな転機を書き出さなきゃ!と思うかも知れませんが、出来事のインパクトの大きさは気にする必要はありません。
洗い出していく中で大切な経験が思い浮かんできます。
高校、大学受験での成功(or失敗)から何気なく友達から褒められた瞬間まで、思いつく限りの経験を紙に書き出していきましょう。
「感情の動き」を分析する
数多くの経験の中から「自分が頑張った!」と思える経験をするに至った背景を考えます。
そして、その背景に対して「なぜ?(=感情の動き)」を繰り返すことで、深ぼりしていきましょう。
例えば、Aさんは、
「サークルの新歓代表として30人程(昨対比+5名)の新入生の勧誘に成功」
という経験がありました。これだけでは、ただの結果のみなので、
「なぜ新歓を頑張ったのか?」
という「なぜ」を与えて考えてみました。するとAさんは、
「一つ上の先輩からの期待に応えたかったから」
というような思いがあったことを思い出しました。
しかし、頑張る理由としては他にも、
「リーダーとして周りを引っ張ることが得意だから」
「自らの交友関係を広げていきたい」
なども考えられますが、Aさんはその中でも特に「周囲の期待に応える」ということにやりがいを感じました。
そのことから、Aさんは「他社貢献意欲」が高いことがうかがえます。
このようにして、自らの印象的な経験に対して深ぼりを重ねていくことで、「モチベーションの源泉」が明らかになっていきます。
「モチベーションの源泉」とは、「やる気を感じる瞬間」とも言い換えられます。
それは、「他人の役に立てる」「困難に挑戦する」「自分にしか出来ないことを成し遂げられる」など人によって様々です。
「モチベーションの源泉」を明らかにすることは、志望業界・職種決定する上で非常に重要なので、時間をかけて行いましょう。
自己分析はいつから始めるのが良い?
ここからは就職活動における自己分析を始める時期について解説していきます。
結論としては、「夏インターン前」がベストです。
以下では、自己分析を重点的に行う時期は大きく分けて3つあります。
夏インターン前(5月~6月)
このあたりから就職活動に向けて動き出す方が多いです。
6月は夏インターンの情報解禁でES(エントリーシート)や面接対策などで忙しくなるため、それまでに自己分析をある程度行っておくと余裕を持って行動できます。
夏インターン前は、自身の「モチベーションの源泉」を明らかにすることに注力しましょう。
ほとんどの企業の夏インターンの面接は、志望理由(=未来)よりも学生時代に頑張ったこと、自己分析(=過去)が重視される傾向にあります。
したがって、これまでの経験の洗い出しやそこでの感情の動きを整理できていれば、面接官が知りたい情報を十分伝えることができます。
秋冬インターン前(10月~11月)
多くの就活生がこの時期の自己分析を怠っている印象があるので要注意です。
この時期は夏インターンを終え、秋冬インターンに向けて志望業界の絞り込みを行っている段階です。
ここでの自己分析を怠ってしまうと、自分の指向性とマッチしない業界を選定してしまい、後の秋冬インターンや本選考に大きな影響を及ぼします。
ここでは、夏で明らかにした「モチベーションの源泉」と、インターンを通して得られた業界ごとの情報(業務内容・やりがい等)を組み合わせて、
「自分が本当にやりたいこと」を明らかにしていきましょう。
「モチベーションの源泉」を業務内容レベルに落とし込んで行くことがポイントです。
私は、
- 他者の目標達成のサポート
- 自分の知らないことに対するチャレンジ
にモチベーションを感じてきたため、
①他者(=お客様)の課題解決を一番近くで支え、②様々な業界の人と仕事ができる「総合コンサルティングファーム」
を第一志望にしました。
こうして、「自分が本当にやりたいこと」を明らかにすることで、秋冬以降の志望業界の絞り込みがスムーズに行えます。
本選考前(1月~2月)
本選考では、学生時代に頑張ったこと、自己分析(=過去)にとどまらず、志望理由からキャリアプランに至るまで様々な角度から質問されます。
そのため、より強固に自己分析を進めていく必要があります。
これまで行ってきた自己分析をもう一度見直すことに加え、「自分が本当にやりたいこと」と志望企業との繋がりについて内容を詰めていきましょう。
企業の繋がりとは、
- 「自分が本当にやりたいこと」と志望企業の特徴との親和性
- 「自分が本当にやりたいこと」の志望企業での実現可能性
の大きく2つに分けられます。
志望企業との関係性の解像度を上げるためには、自分のことだけではなく、相手(=志望企業)に対する理解度を上げることが必要不可欠です。
本選考前では、自己分析に加えてOB訪問やIR資料を読み込むことで企業分析の充実にも努めていくのが良いです。
自己分析をする前後の変化
私は就職活動を始めた時、自己分析のやり方がよくわからず後回しにしていました。
「自分のことは自分がよく知っている」と慢心していた私は、初めての面接で面接官の自己分析に関する質問に何一つ答えられずに無事爆死しました。
その後、自己分析に関する書籍や記事を読み漁り、対策することで「自分が真にやりたいこと」を言語化できるようになりました。
自己分析によって変わることを具体的にご紹介します。
面接で自信をもって話せるようになった
就職活動の面接では必ずと言っていいほど「自己分析」に関する話題が質問されます。
自己分析を重ねることで、そうした頻出事項に対する答えの精度が必然的に上がります。
それにより、「面接で自己分析系の質問が来ても大体は上手く答えられる」という精神的余裕が生まれ、自信をもって話すことが出来ました。
発言内容に一貫性が生まれた
自己分析を重ねることで、「自分がどういう人間か」「真にやりたいことは何か」が明らかになり、予想だにしない質問に対してもぶれることなく答えられるようになりました。
面接官は目の前にいる就活生がどんな人かを知りたがっています。
自分の軸がぶれずに面接を進めていくことで、面接官に自分という人間の中身を伝えやすくなります。
おすすめの本、サービス
私が就職活動中の自己分析でお世話になった本を2つ紹介します。
どちらも非常に役立つため、購入を勧めます。
・ストレングスファインダー
・絶対内定
まとめ
本記事ではこれから就職活動を控えている方に「自己分析」の方法についてお伝えしてきました。
私は就職活動を通じて、自己分析は就職活動時だけではなく、今後の人生において非常に大切なことだと強く感じました。
自己分析で「自分が真にやりたいこと」を明らかにして納得行く就職活動になることを願っています。