

大学院生活は思っている以上に、多くのことを学べて、同じくらい悩み続ける生活を送ります。
私は外部進学をしたこともあり、毎日が忙しく目の前のことをこなすので精一杯でした。
なので、今になって後悔することとかあるんです。
「もっと就活の準備を前もってすればよかった」
「もっと研究を真剣にしておけばよかった」
「もっと積極的に行動すればよかった」
あなたにはそんな後悔をして欲しくない。という気持ちで、この記事を書いています。
この記事では、
- 大学院生活の流れ
- 研究で役立つツール
- 休学や中退の悩み
- 大学院生の就活
など、大学院の生活で感じたことや学んだこと、気付いたことを紹介していきます!
これを読んでくれたあなたが、充実した大学院生活を送り、卒業したときに、
「大学院に通ってよかった」
と思っていただけたら幸いです。
大学院生活の流れ
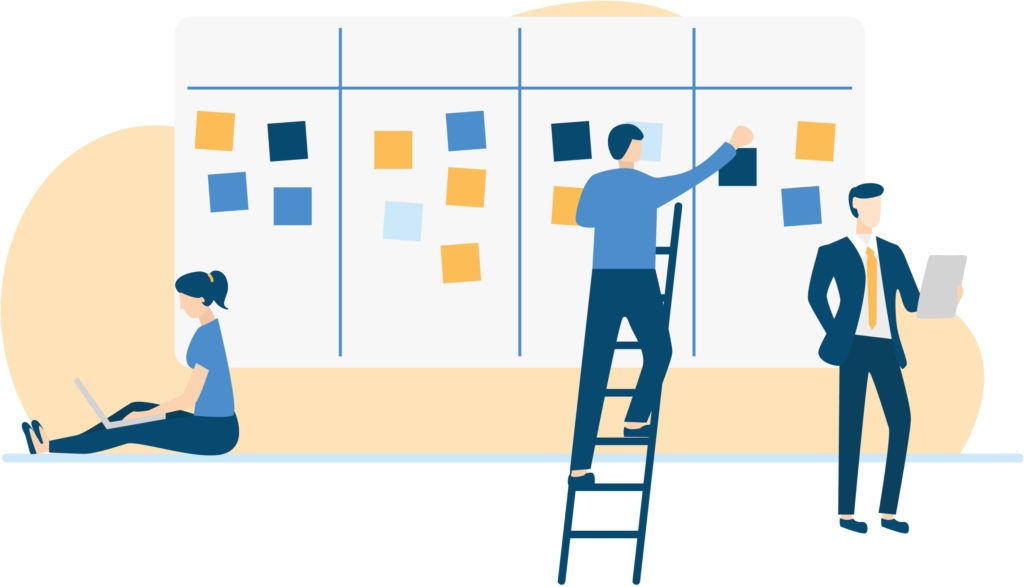


大学院でしないといけないことは、こちらです!
- 研究
- 授業・講義
- 雑誌会・勉強会
- 研究発表
- 学会
- 就活
- 論文執筆
- 卒業論文
これらの内容について一つずつ紹介していきますね。
大学院生活は意外と短く、常に何かやることが待っています。
大学院生の1年間の生活、1週間の生活、1日の生活はこの記事にまとめました。
理系の院生は、昼も夜も関係なく研究をしている人が多いです。
私の研究室ではコアタイム(研究室にいないといけない時間)が決まっていたので、昼夜逆転はありませんでしたが、研究室によっては「夜に来て朝に帰る」という人もいます。
「え…あの人いつ来てるの??」っていう人もいます。
これまでの「学生生活の常識」が通じないのが研究室生活です。
研究:大学院生の大半の時間を使う
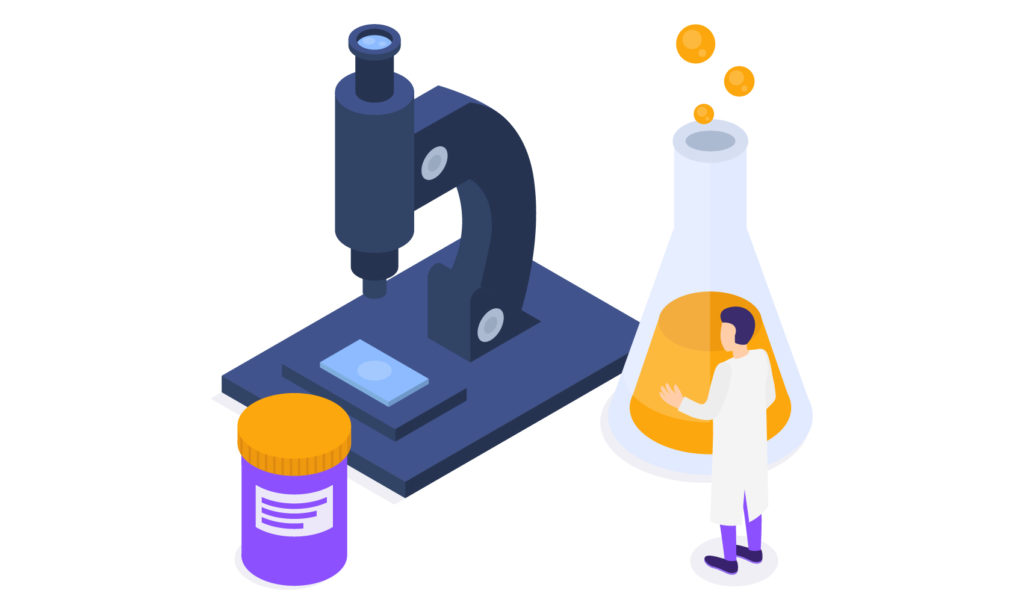


研究は大学院で一番しないといけないことです。
与えられたテーマについて、新しい発見をするために毎日実験をします。
あまりにやらなかったら、卒業できずに留年することも普通にあり、博士課程では論文を何報か発表しないと卒業できないところも多いです。
いかにして、研究で結果を出すかを考えないといけません。
しかし、結果が出なくても修士なら卒業はできます。
結果を出せると生活に余裕ができて、
- 夜遅くまで研究しなくてもいい
- 就活も自由にできる
- 卒業論文も早く書ける
- 発表でも堂々とできる
など時間と心にも余裕ができますし、得られる力も多いので、できるだけ頑張りましょう。
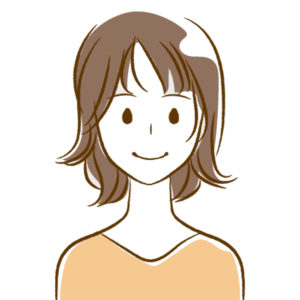

研究するのに役立つツール
今でも研究者をしているんですけど、私が大学院生の時に使ってたり、大学院生におすすめできるツールを紹介します。
1. 論文・文献管理ソフト「Mendeley」
Mendeleyは日々積もっていく論文や文献を管理してくれる無料ソフトです。
論文を探す手間が省けるので、おすすめです。
2. マインドマップソフト「Xmind」
Xmindはマインドマップを作成するツールです。
メモリーツリーと原理は近いです。
あわせて読みたい
私はXmindを使って研究背景をまとめたり、就活の時の自己分析に使っていたりしました。
考えや情報をまとめたいときに便利なツールです!

3. DeepL
DeepLはGoogle翻訳の超すごい版です。
学術的な内容もしっかり翻訳してくれます。
授業・講義:修士1年で大体終わる

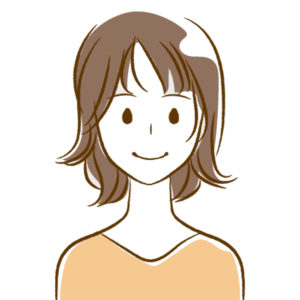

大学院生にも必要な単位が決められているので、授業や講義は受けなければいけません。
大学院の授業は、大学より専門的な内容となるので難しいです。
でも、授業に時間を使うのはもったいないので、1年生のうちに必要な単位を全て取っておくことをおすすめします。
雑誌会・勉強会:怒られないようしっかり準備しよう



私の研究室では「雑誌会」と「勉強会」と呼ばれるイベントがありました。
雑誌会
→ 最新の論文を紹介する会
勉強会
→ 装置の原理や研究の歴史などを体系的に教える会
他の研究室でも、名前は違っても似たような会が開かれていると思います。
これが、かなり厄介なんですよね。
準備に時間かかるし、出来が悪いとやり直しさせられたり、怒られたりで。
1ヶ月以上前からコツコツ準備することをおすすめします。
私の研究室では留学生が多かったので、英語で発表しないといけなかったりしました。
その分、英語力や思考力、プレゼン能力などの多くの成長があるので、しっかり取り組みましょう。
研究発表:この出来次第で大学院生活が変わる
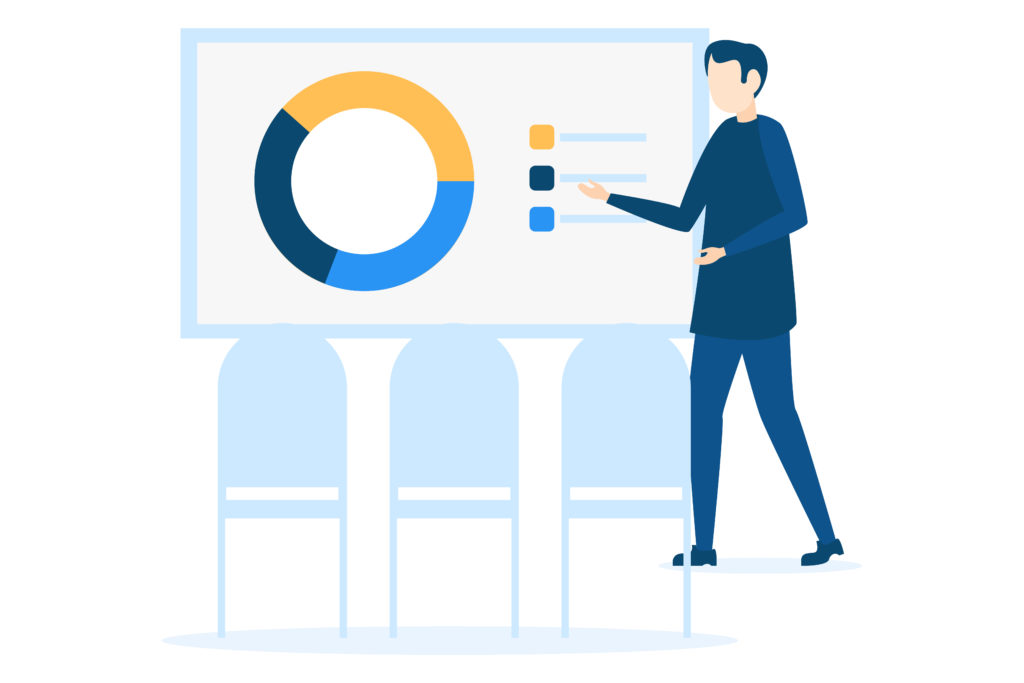
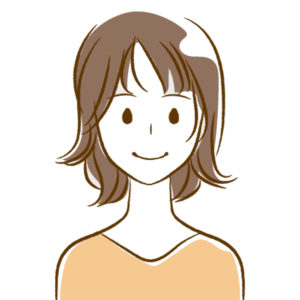

数ヶ月に1回やってくる研究発表です。
このウェイトも重いんだ…本当に。
私の研究室では、2種類の研究発表がありました。
- 教授陣を含めた研究室のメンバーだけで行う報告会
- 外部からお客さん(教授や研究者)を招いて行う報告会
研究結果が出ていれば、ある程度安心ですが、結果がないと食事も喉を通らないほどに辛かったです。
ちなみに、私は修士一年の間はずっと怒られ続けていたので、ただの怒られイベントでした。
怒られ続けたおかげで、精神的なタフさとプレゼンの技術が身につきました。
あなたも、頑張ってね…!!
大勢の人の前で発表する経験はなかなかできませんし、研究に対するコメントも頂けるので貴重なイベントです。
あとは、外からのお客さんを招いた時は、学生で司会進行をしていたので発表者への「質問」を考えるのが辛かったです。
質問を考える力は社会人になってからも役立ちました。
辛い思い出ばっかり出てきて、すみません笑
辛い思い出にならないために、役立ちそうな情報を紹介していきます!
いい発表をするための技術:プレゼン力
いい発表には、理由がちゃんとあります。
私が研究生活で学んだプレゼンの技術をこちらの記事で紹介しています。
学会:参加できると大学院生やってる気分になるイベント
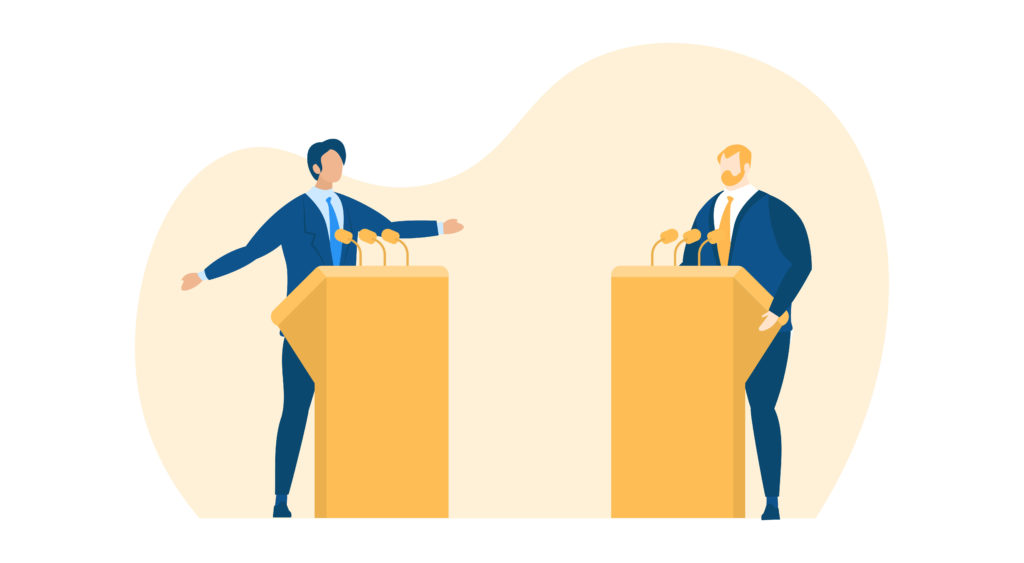
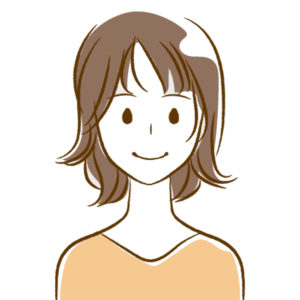

学会は報告会の規模をめちゃくちゃ上げたバージョンです。
全国から研究者達が集まって、自分たちの研究の発表や他の人の研究を知るためのイベントです。
学会発表には2種類あります。
- ポスターセッション
- 口頭発表
1つめのポスターセッションは1枚の紙に研究をまとめて、会場でポスターを貼って、人が見にきた時に発表をします。
大体2時間ぐらい立って、研究者の人たちと話すイベントです。
2つめの口頭発表は1つの会場を使って、多くの人の前でスクリーンとパワポを使って研究発表をします。
時間は20分ぐらいで終わりますが、ポスターに比べて人の数が半端じゃないので、こっちの方が私は緊張しました。
ポスターは別に質疑応答ができなくても、聞いてくれたその人だけに申し訳ないだけです。
しかし、口頭発表は会場にもよりますが、100人以上の人の前で恥をかくのでプレッシャーが半端ないです。
さらに海外の学会だと、英語なのでさらにハードルは上がりますね。
英語での発表は台本を作ってまる覚えすると意外とできます。
伝わってるかはわかりませんけどね笑
学会の参加経験は就活の時にも役立ちますので、経験を積んで損はないです。
あわせて読みたい
就活:修士で卒業するなら、むしろ一番力を入れるべき



修士の人だと、1年の終わりぐらいから就活が始まるので、時間が足りません。
そのため、就活は1年のうちから早めに取り組んでおきましょう。特にインターンは参加しましょう。
私は、業界は希望するところに就職できましたが、もっと早くから取り組めばこんなに苦労しなかったのに…って後悔しています。
インターンシップは積極的に行った方がいいですし、研究室のコネも希望する企業があれば使った方がいいです。
私が苦戦した就活をもとに、おすすめの就活サイトや自己分析の方法などを紹介していきます。
自己分析の方法
まずは、自己分析をして「自分がどんな生き方をしたいか」を考えましょう。
当サイトの現役学生ライター達が実際に行った自己分析の方法はこちらです。
あわせて読みたい
手軽で正確な自己分析をするなら、適性検査サービスを複数受けるのがおすすめです。
それにより、自分が気づかなかった新しい一面を知ることができます。
私が実際に使った、自己分析サービスを紹介します。
1. Future Finder
Future Finderの適性検査の詳しさと正確さはこれまでやってきた中で1番でした。
2. キミスカ適性検査
キミスカ適性検査では、適性の他に「自分が嘘の回答をしていないか」を知ることができます。
自分の考えが一貫しているか知ることで、芯のある志望動機を考えることができます。
3. OfferBox
OfferBoxの「AnalyzeU+」は自分の能力を他者と比較して偏差値で出してくれるので、長所短所がはっきりと分かります。
就活を失敗しないためには
私は満足のいく就活ができませんでした。
その時に、感じた就活について書いた記事です。

就職浪人した友人の話
研究が忙しくて就活がうまくいかず、就職浪人してしまう方もいます。
私の友人にも、就職先が決まらずに浪人した人がいますが、彼らはうまく就活をして、納得いく企業で働いています。
もし、現役中に内定がもらえなくても、絶望しないでください。
あわせて読みたい
論文執筆:在学中にできたら堂々と卒業できる勲章
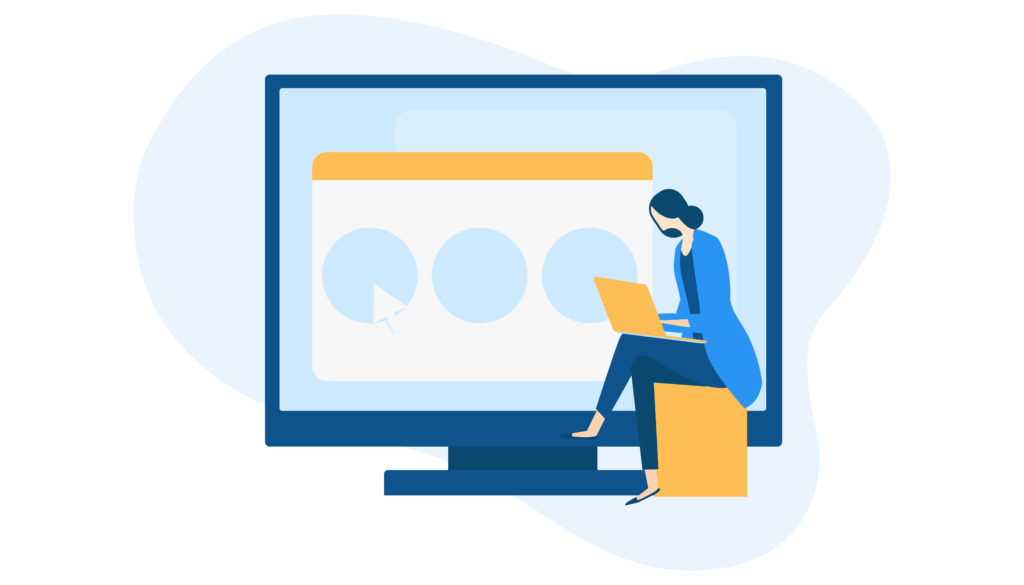


研究者としての成果の数は「論文の数」と言っても過言ではありません。
学生のうちに論文が出るくらいの結果を出せたら、最高ですね。
論文を書くのは、教授の主導のもとになるでしょうが、実験項については実施者である学生が書くことになることもあります。
普段から実験をまとめる癖をつけておくと、後々楽ができます。
論文は書くのも大変ですが、論文にするためのデータどりも大変です。
- チャンピオンデータをとったり
- 不足している条件検討を足したり
- より精密な桁数まで測るための測定を行なったり
- 実験操作をブラッシュアップしたり
- 論文用のグラフや図を作成したり
論文に穴がないようにしていく必要があります。
学生のうちに論文を出せれば、就活の時の強みとしても活かせるので、論文目指して頑張りましょう!
卒業論文:めちゃくちゃでも期限はしっかり守ろう

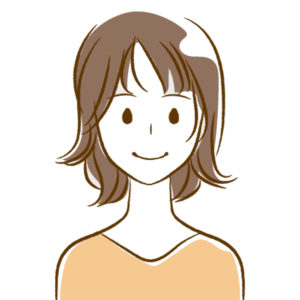

卒業が近づいてくると、修士論文や博士論文が待っています。
自分の研究の集大成です。
卒論は早い人で卒業の半年前ぐらいから、遅い人で3ヶ月前ぐらいから始めていました。
卒業論文は日頃から実験の結果を図や表にまとめていたり、実験項を作っていれば楽になります。
どれくらい書くかというと、私の時は60〜70ページぐらいだったと思います。
研究分野によって枚数は違うので、参考に留めてください。
あわせて読みたい
大学院生活の悩みなど

ここからは、大学院生活で感じた悩みや不安などについての記事を紹介します。
外部進学が辛い
私も外部進学組だったので、大学院生活は辛かったです。
でも、辛いからこそ得られるものは大きいです。
あわせて読みたい
中退や休学を考えている
大学院は中退や休学をする人が多いです。
私も卒業する頃には3割もの人が減っていました。
でも、中退や休学は別に悪いことではないです。
中退や休学をした友人が、今どんな人生を歩んでいるか紹介しています。
中退して就活をする場合、中退者専門の就活サービスを使うと就活が楽になります。
また、辞めようと考えている人はこちらの記事を読んでみてください。
それでは、よい大学院生活を!
